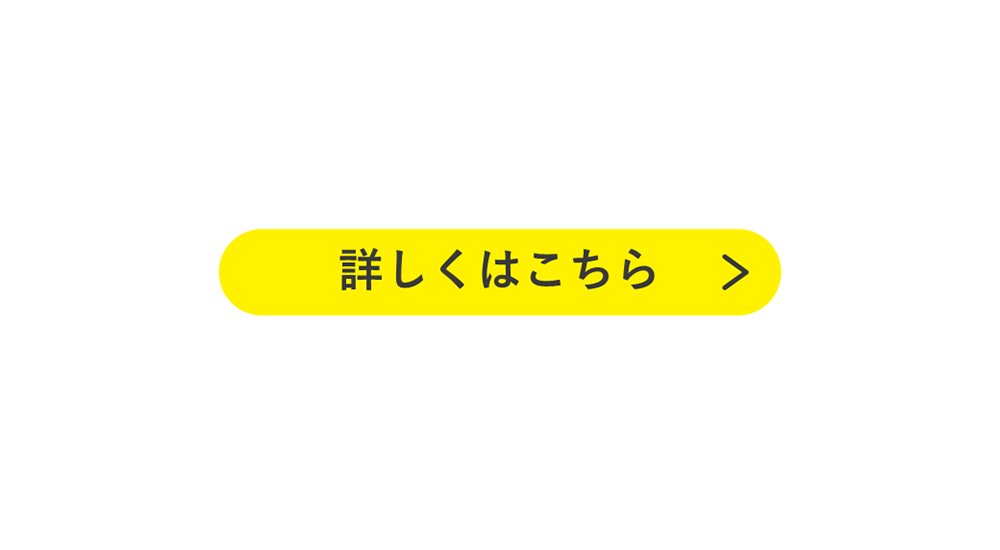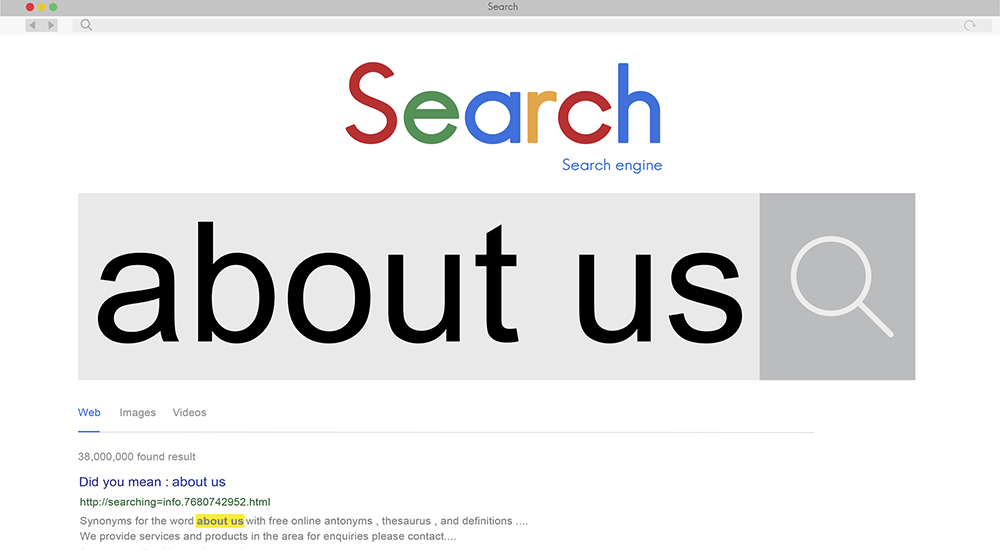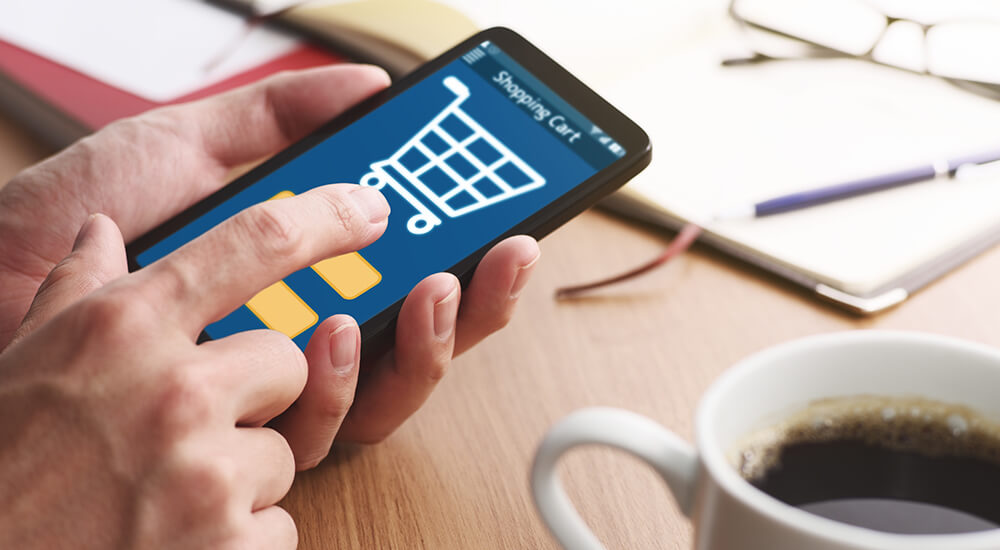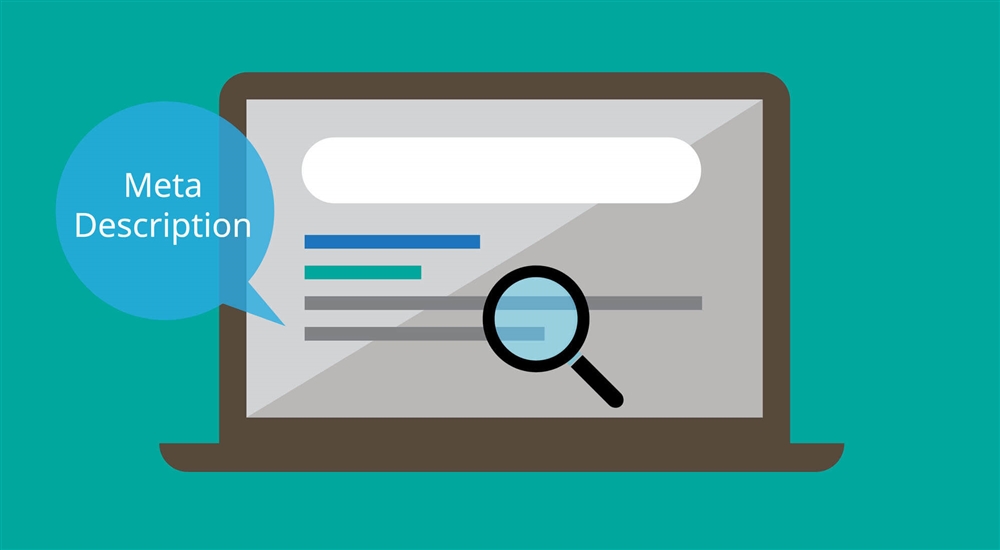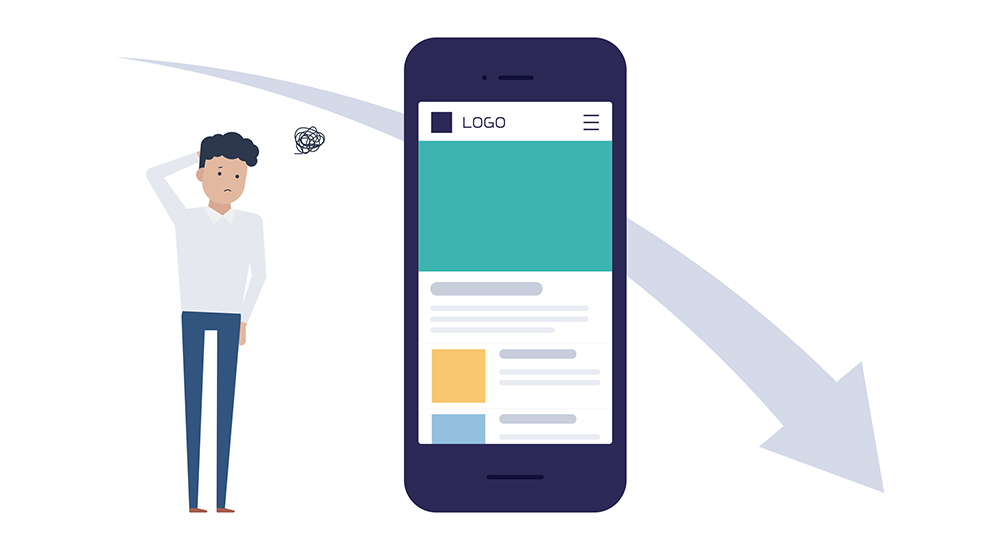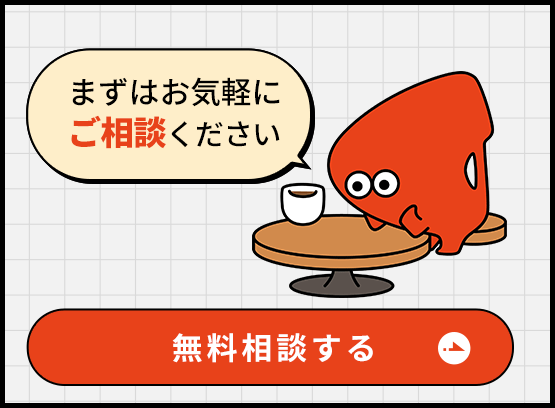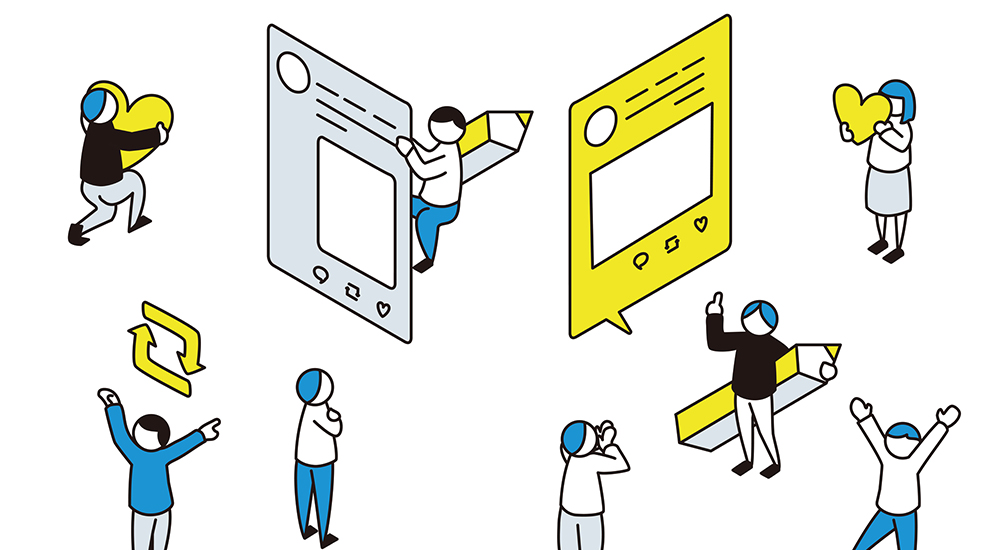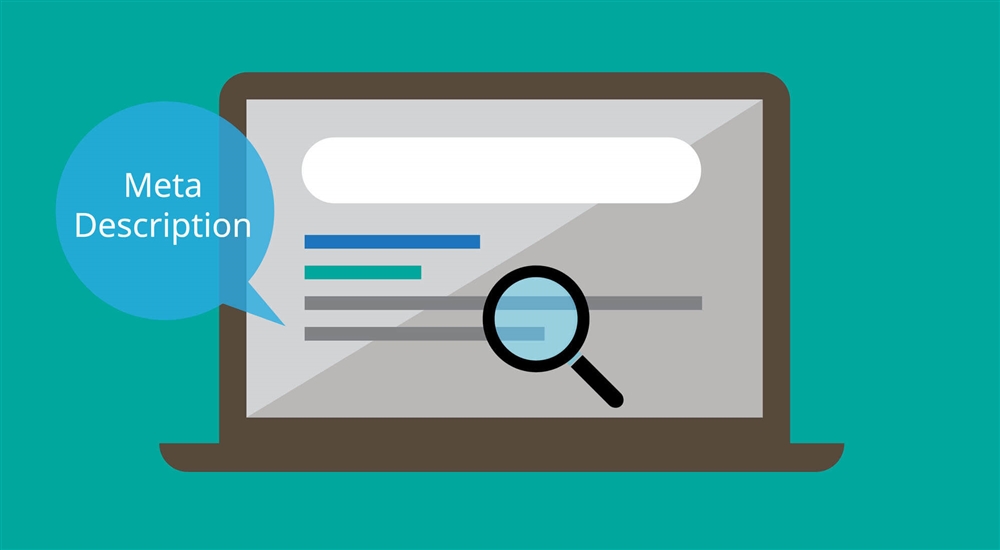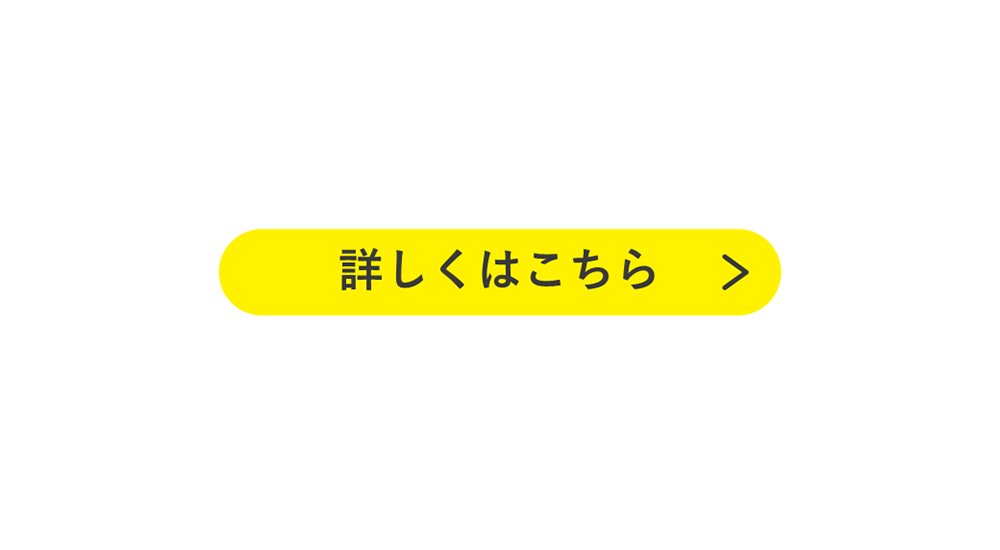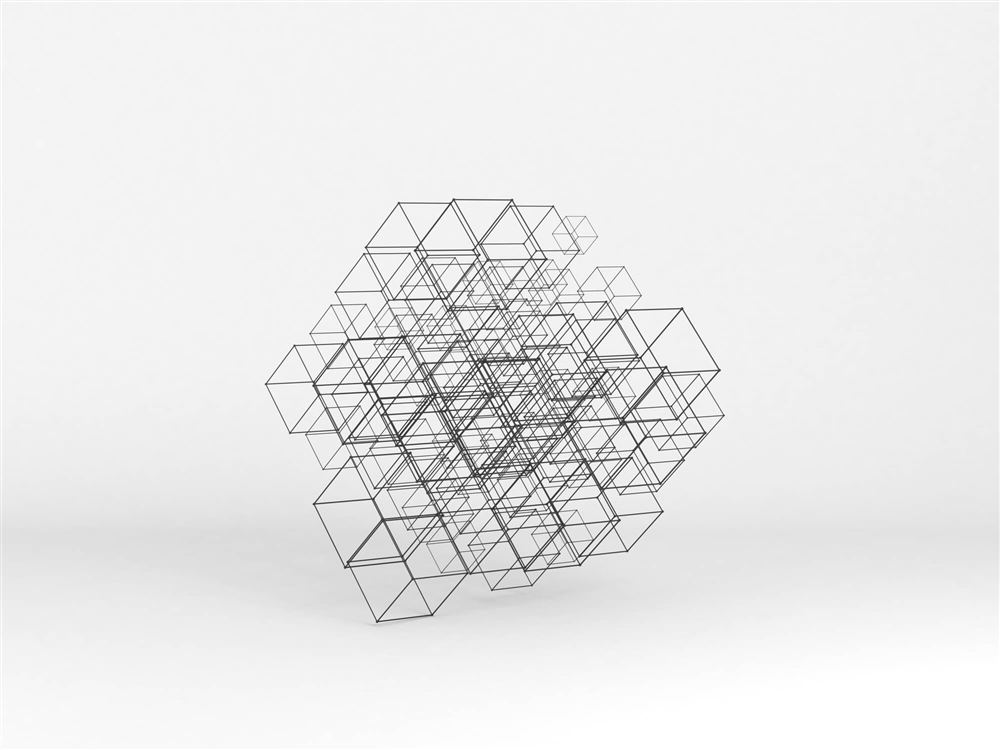販促カレンダーを活用すると、施策や配信の年間計画が立てやすいだけでなく、来期に向けて施策のブラッシュアップもしやすくなります。PDCAを回しながら運用していくことが可能となり、ECサイトの成長をさせていくには欠かせないツールです。
こちらでは「販促カレンダーを活用して施策の年間計画をたてたいけど、作り方がわからない」「月ごとにやる施策のアイディアがわかない」という方に向けて、販促カレンダーの作り方や、作るうえで参考にしたい情報、作成時のポイントなどをご紹介します。
OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。
販促カレンダーとは
販促カレンダーとは、季節ごとのイベントや年間行事が記載されたカレンダーのこと。
ECサイトでは売上目標達成のために、セールやクーポンの発行、サンプル配布、ポイントアップキャンペーンなどさまざまな施策を実行していくと思いますが、それらの施策を考えるうえで季節のイベントや行事といった顧客のニーズに関する情報を把握することは非常に重要です。
販促カレンダーを活用し、顧客のニーズをキャッチすることができれば、売り上げにつながる施策を考えやすくなります。また、季節ごとのイベントや年間行事とあわせて施策やその結果を販促カレンダー上で一元管理しておくと、来期に向けた施策も考えやすくなります。
目標達成に向けて戦略的にECサイトを運用していくなら、販促カレンダーは欠かせないツールです。
販促カレンダーはなぜ必要?
販促カレンダーを作成するのは大変ですが、作成することで売上目標達成のために活用できたり、予算を確保できるなどのメリットがあります。
また、実際に施策を進める際にもリソースが確保しやすい、連携がスムーズになるなどの効果も。ECサイトの運用を効率的に行うなら販促カレンダーは必要不可欠なツールです。
売上目標達成に活用できる
目標としている売上を達成するために販促カレンダーは欠かせないツールです。ECサイトの売上を伸ばしていくには、売れどきを外さないことが重要です。とくに季節性商材の場合は、特定の時期にニーズが急増します。
販促カレンダーで年間のイベントや季節ごとの行事を把握できていれば、ニーズが急増するのを狙い、施策を計画的に実施できます。これなら売れどきを逃すことはないので、売上の最大化も期待できます。
予算確保と管理に使える
販促カレンダーを作成して、各施策の予算を明確化することで、年間あるいは特定の期間の予算をおさえることができます。また、カレンダー上でも予算の状況を確認できるので、限られた予算を効率的に配分できるほか、無駄な支出を抑えることもできるでしょう。
年間計画をたてずに場当たり的な運用では予算を確保するのが難しく、施策を実施することも叶わなくなってしまいます。
関係部署や社外との情報共有
販促カレンダーは施策の管理だけでなく、関係部署との連携や、社外との情報共有に活用することができます。
いつまでに、何を実施するのか?関係者との認識を一致させることで、それぞれが何をやるべきかが明確になり、スムーズに施策を進めやすくなります。
各施策を余裕をもって進められる
販促カレンダーを作成して年間計画をたてておくことで、各施策を余裕をもって進められるというメリットもあります。
あらかじめ何をやるかがわかっていれば、余裕を持った進行が可能になります。商品選定や商品の確保に時間をさけるので目玉商品を用意できる、ニーズの調査に時間をかけられるなど、施策を成功させるための準備がしっかりとできるでしょう。
無計画な運用では施策が立て込んでしまう可能性があります。そうなるとクリエイティブの質が落ちたり、施策でやりたいことがあっても妥協が必要になったりと満足のいく施策を実施することが難しくなります。
リソースを確保できる
施策をするうえで特集ページ(LP)やメルマガ、バナーなどの制作が必要になるでしょう。年間計画をたてておくことで、制作に必要なスタッフをおさえておくことができるのでリソース不足に困ることはないでしょう。
突発的な依頼では、スタッフを確保することが難しくなります。対応可能なスタッフを探すのに時間がとられてしまっては、狙っていた販売期間に施策を実施することが困難になり、売れどきを逃してしまうリスクがあります。
振り返りがしやすくなり運用の効率化が可能に
販促カレンダーに売上目標や成果を記録しておくことで、各施策の効果測定がしやすくなり、来期に向けた施策を考えやすくなります。
ECサイトの施策を毎年1から考えていくのは大変です。効率よく運用するなら好評だった企画は継続し、改善が必要な企画はブラッシュアップしていくという形で進行するのがいいでしょう。
施策の結果にもよりますが、継続して運用するという方法ができれば、すでに進め方が身についているので今期より効率的に進められます。
販促カレンダーをもとに運用を効率化するなら、施策実施後に、振り返りがしやすいように今期の販促カレンダーにデータをまとめておくのが理想です。
できれば、良かったことや悪かったこともカレンダーに記録しておくのがいいです。その時は覚えていても日々の運用が忙しく、何があったのか忘れてしまうものです。
目標としていた売上達成ができたのなら何がよかったのか?次回以降に生かせるポイントを具体的に記載します。未達の場合は改善点を記載しておくことで来年度も同じ失敗をしてしまうのを防げるでしょう。
販促カレンダーの作り方
続いては、販促カレンダーの作り方をご紹介します。初めて販促カレンダーを作る方はもちろん、自己流で販促カレンダーを作っている方は、作り方があっているか確認していきましょう。
ステップ1:現状分析と目標設定
まずは、実施した各施策の分析と来期の目標設定をします。分析するものとしては以下が挙げられます。
- データ分析:売上高、CVR、客単価、ユーザー数など
- ユーザーの情報:新規顧客かリピーターか、流入元、性別、年齢、居住地、直帰率など
- 競合他社の販促活動
売上をあげるには、訪問するユーザー数を増やす、訪問したユーザーの中から購入する人を増やす、使ってもらえる金額を増やすという3点を改善する必要があります。売上が未達の施策があった場合は、先ほどの3点のうち、どこかに要因があるといえます。
季節性商材を販売する場合は、時期は去年と一緒でいいのか検討が必要です。たとえば、おせち特集の場合、他社が10月から動き始めているのに自社が11月から販売開始している状態では、顧客を奪われてしまう可能性があります。競合他社の状況やニーズが高まる時期を調査しましょう。
現状の分析ができたら来期の目標を立てます。目標を立てる際は具体的かつ測定可能な目標を設定しましょう。
ステップ2:ターゲットとテーマの設定
誰に商品やサービスを届けたいのか?そのためにはどのようなキャンペーンが必要なのか?考えていきましょう。ステップ1で分析したユーザーの情報をもとに検討するといいでしょう。
キャンペーンを考える際は施策の目的や時期、予算を明確にすると、具体的に施策内容を決定するためのステップ3の工程が考えやすくなります。
ステップ3:具体的な施策の決定
ターゲットとテーマが決まったら、具体的に施策内容を考えていきましょう。
売り方はセールなのか、クーポン発行なのか、ポイントアップなのか?どのような商品があると売り上げを上げられるのか?など詳細に考えていきます。
このタイミングで決めておきたい内容の一例を以下に記載しています。
決めておきたい内容の一例
・実施時期
いつからいつまで実施するのか
・ターゲット
誰にむけた販促活動なのか
・販促テーマ
どのようなテーマでキャンペーンを実施するのか
・販促内容
具体的な販促施策(セール、クーポン配布、新商品発売など)
・担当者
誰が責任者となって実行するのか
・予算
各施策にどれだけの予算を割り当てるのか
・KPI、目標値
施策の成果を測る指標とその目標値
ステップ4:カレンダーへの落とし込み・情報共有
ステップ3で具体的な内容がまとまったら各施策を販促カレンダーに落とし込んでいきます。
販促カレンダーにまとめたら、関係者へ内容を伝え、承認を得ましょう。承認が得られたら関係部署へ販促カレンダーを共有し、各担当者が実施に向け動き出していきます。
ステップ5:効果測定と改善
各施策を進行しながら 設定したKPIに基づいて、各販促施策の効果測定をしていきます。改善点があれば来期に生かすために販促カレンダーにメモしておきましょう。
販促カレンダー作成のポイント
販促カレンダーを作成する方に向けて、おさえておきたいポイントを5つご紹介します。
修正しやすい作りにする
社会情勢などによって年間計画通りに運用ができないケースもあります。そういった場合は必要に応じて計画を変更し、柔軟に運用していくことが求められます。
柔軟な運用がしやすいように、販促カレンダーも修正しやすい作りにしておくのが理想です。レイアウトが複雑だと修正に時間を要してしまい、作業者の負担が大きくなります。
関係各所への共有は必須
販促カレンダーを作る際は、関係各所への共有を必ず行いましょう。たとえば、施策を決めても実施するうえで必要な商品が用意できないとなると施策を再度考え直す必要があります。
これでは無駄な工数がかかってしまいます。担当者の大きな負担になるだけでなく、来期に向けた販促カレンダーの準備が大幅に遅れてしまうリスクも。
関係各所へしっかり共有をしておくことで、やり直しなど二度手間になってしまうことを回避できます。ただし、さまざまな方の意見を聞くことになり、企業によっては確定まで時間を要します。
こういったことをふまえ、販促カレンダーを作る際は、余裕をもって進めるのが望ましいです。できれば来期が始まる2~3か月前に作成しておくと安心です。
見やすく、共有しやすいものにする
販促カレンダーは作った本人だけでなく、社内外の関係者も使うツールです。自分だけがわかるものではなく、誰がみてもわかりやすく、誤認が起きないような作りにしましょう。
販促カレンダーを1から作るのはなかなか難しいと思いますので、ダウンロード可能なテンプレートを活用して最適な形にしていくといいでしょう。
また、企業によってはクラウド上で編集可能なファイルの使用がNGの場合もありますよね。作ったあとに「その形式では見られません」とならないように、あらかじめ関係者が閲覧可能なファイルを確認しておくといいでしょう。
仮でもいいので配信日も決めておく
販促カレンダーを作る際は、メルマガなどの配信日もあらかじめ決めておきましょう。ただ、販促カレンダーを作成する時点では配信日を確定できないと思いますので仮のスケジュールでも大丈夫です。
1日に配信可能な回数が決まっているなど、企業によっては配信に関するルールを設けている場合もあるでしょう。事前に配信日を決めておくことで後々、配信がバッティングしてしまうことを防げます。
一般的なイベントだけでなく独自のイベントも検討
販促カレンダーでは、定番の行事や季節のイベントだけでなく、自社独自のイベントも実施できないか検討しましょう。
季節ごとにあるイベントは競合他社も実施することが予想され、差別化するのが難しいです。ほかにはない独自のイベントを行い、顧客との関係性を深められないか考えましょう。
たとえば、ECサイトであれば商品を売ることにフォーカスしてしまいますが、それだけでなくユーザー参加型の施策を実施してみるなどです。施策に参加するのをきっかけに顧客にサイトの利用を促したり、商品購入のきっかけをつくることが期待できます。
独自のイベントが顧客に好意的に受け取られれば、企業に対する親しみや愛着を向上させることもできるでしょう。
おさえておきたい月別の行事一覧
こちらでは月別にイベントや予想される季節需要などを記載しています。年間計画を考える際にアイディアに行き詰まったらこちらを参考にしてみてください。
1月
主なイベントや季節需要
お正月、初詣、成人の日、受験、七草がゆ、初売り、福袋、寒さや乾燥対策、韓国旧正月、中国春節
1月は初売りや初詣の時期なので、それにちなんで新春セールや、運試しが楽しめるおみくじクーポンを施策として取り入れてみてはいかがでしょうか。
また、ターゲットが若年層であれば新成人の方にお祝いとして該当者にクーポンを配布するなども考えられます。
越境ECを運営している場合は春節など海外のお正月の時期にあわせてキャンペーンを実施するのもいいですね。
2月
主なイベントや季節需要
バレンタインデー、節分、恵方巻、受験、花粉症対策
バレンタインデーはチョコレートに限らず、スイーツのニーズが高まる時期です。スイーツで特集を組むのもいいですし、食品を扱っていなければギフトにおすすめの品物を訴求するという切り口もあります。
2月は花粉症が飛び始める時期でもありますので花粉症対策ができるグッズをお得に販売するなども挙げられます。
3月
主なイベントや季節需要
ひな祭り、ホワイトデー、卒園・卒業式、卒業旅行、新生活に向けた準備(引っ越し、就職、進学、転勤)、お花見
3月は進学や就職など新生活に向けて準備をする時期なので、インテリアや家具家電の需要が高まります。新生活応援キャンペーンと称して、インテリアや家具家電をお得な価格で提供してみては?
4月
主なイベントや季節需要
お花見、入園・入学式、入学祝い、ゴールデンウィーク
4月は新生活がスタートする時期。通勤・通学や学生生活、仕事に必要なアイテムのニーズが高まると予想されます。施策でもカバンや服装、PC関連アイテムなど新生活にちなんだアイテムを取り扱ってみてはいかがでしょうか。
また、新社会人にとって服装は?持ち物は?など、気になるものです。商品の訴求だけでなく、社会人としてどのような選択がベストなのか、そういった情報を織り交ぜながら特集ページを作ってみるのもいいでしょう。
5月
主なイベントや季節需要
ゴールデンウイーク、キャンプ・バーベキューなどのアウトドア、こどもの日、母の日、衣替え
5月には楽しい連休があるものの、学校や会社が休みの分、3食作る必要があり毎日の自炊が負担になる時期です。自炊の負担が減るようなキッチングッズや、焼くだけなどカンタンに食べられるグルメ系の訴求もアイディアとして考えられます。
また、大型連休は各地混雑が予想され、おうちで過ごすことを選択する方もいらっしゃるでしょう。おうち時間を楽しめるグルメや雑貨、ゲームなどを訴求するのもいいですね。
6月
主なイベントや季節需要
父の日、梅雨、レイングッズ、暑さ対策、カビ対策
梅雨シーズンなので、洗濯物を早く乾かせるグッズ、布団の湿気対策、レイングッズ、撥水機能のある衣類、レインブーツなどのニーズが高まります。
しかし、梅雨対策特集は今では定番の特集になっており、各社似たような内容になるのが難点。余裕があれば差別化できる打ち出し方はないか考えてみましょう。
7月
主なイベントや季節需要
七夕、花火大会、夏祭り、浴衣、水着、海、プール、夏休み、夏フェス、台風、熱中症対策、紫外線対策、夏バテ、土用の丑の日
楽しい夏休みシーズンが始まりますが、厳しい暑さが予想されるので熱中症対策や紫外線対策ができるグッズを訴求するのもおすすめです。
暑さで食欲低下や自炊意欲の低下も考えられるので、夏バテ予防になる食品や時短調理が可能なグッズなどの訴求もいいでしょう。
8月
主なイベントや季節需要
お盆(帰省)、防災週間、高校野球
8月30日~9月5日まで防災週間になるので、防災グッズや非常食などの準備または確認を促す特集を実施してみては。不足している備えがあると気づけば、特集ページからの購入も見込めます。
また、帰省や旅行シーズンでもあるので、キャリーケースなどトラベル関連のグッズを訴求するのもいい時期です。
9月
主なイベントや季節需要
防災の日(9月1日)、敬老の日、シルバーウィーク
9月は敬老の日があるので贈り物の需要が見込めます。贈り物として選ばれるのは物だけとは限りません。一緒に過ごす時間を楽しめる体験型のギフトも喜ばれます。
10月
主なイベントや季節需要
ハロウィン、運動会、衣替え
季節の変わり目でもある10月は体調を崩しやすい時期です。風邪対策として除菌グッズやマスク、加湿器の活用が提案できるほか、健康なからだづくりとして運動グッズや睡眠グッズ、健康食品の提案に活用してみては。
早い企業では、おせちの早期受付を始めています。自社でもおせちを取り扱っているようなら、競合に顧客を奪われないように早めのスタートがおすすめです。
11月
主なイベントや季節需要
七五三、いい夫婦の日、勤労感謝の日、紅葉、ボジョレーヌーボー解禁、ブラックフライデー、寒さ対策
冬に向けて寒さ対策として暖房器具や冬物、鍋などのニーズが高まります。季節需要が見込まれる商材を取り扱っているなら、お得に買える機会を用意してみてはどうでしょうか。
また、勤労感謝の日を活用して顧客の忙しい日々をねぎらう企画を実施することも案として挙げられます。
12月
主なイベントや季節需要
クリスマス、大晦日、帰省、忘年会シーズン
12月はクリスマスがあり、顧客の購買意欲が高まる時期です。贈り物やグルメ、クリスマス用のインテリアや、クリスマス限定商品などを用意し、購入を後押ししてみては。
また、年末は大掃除の意欲が高まる時期なのでお掃除グッズや掃除代行サービスなどを訴求するにはぴったりな時期といえます。
販促カレンダーを作るうえで参考になる情報
最後に、販促カレンダーを作るために参考にすべき情報をご紹介します。
自然条件
季節性商材を取り扱っている場合は、自然条件(天候や気温など)を参考に施策の開始時期を検討しましょう。
注意点としては、近年は異常気象により施策時期見極めが難しくなっているということ。2024年は10月でも30℃を超えるなど夏が長期化しているため、柔軟な対応が求められます。
秋になってから作り始めるのでは競合にニーズが奪われてしまう可能性もありますので、あらかじめ特集を作っておいて、季節の変わり目がきたらすぐに掲載開始するなど対応を工夫してみてください。
顧客ニーズ
季節要因だけでなく、オーダー数の多い商品を確認して、顧客のニーズをもとに施策を考えるという方法もおさえておきたいですね。オーダー数の多い商品を抽出した後に、なにか関連性はないか確認してみましょう。
たとえば、カニやおせち、お肉、うなぎといった贅沢グルメ系の売れ行きがよければ、贅沢グルメが求められていると判断できます。同様の商品を強化し、売りにつながる新たな施策を検討してみてはいかがでしょうか。
イベント
施策を考える際は、国民の祝日、季節のイベント、地域ならではのイベント、業界イベント、○○の日なども参考にしましょう。
たとえば10月1日はメガネの日、10月10日は目の愛護デーなので、メガネメーカーのJINSは10月をメガネ月間としてキャンペーンを実施していました。業界ならではのイベントはインパクトや面白みがありますよね。
定番のイベントはもちろん、業界や商品、会社にちなんだ工夫を凝らしたキャンペーンはできないか考えてみましょう。
社会現象
売上が順調にのびているなど、運用状況に余裕があれば差し込みの企画を実施してみてはいかがでしょうか。
話題のニュース、流行、社会問題など社会現象を考慮し、トレンド感のある施策を実施することができれば、盛り上がっているニーズをキャッチし、売上拡大を狙えるでしょう。
過去の施策や競合の施策も参考にする
過去のキャンペーンで効果が高かったものはもちろん、競合他社のキャンペーンも参考にするといいでしょう。
競合が行っている施策内容からどの商品を、どのような方法で訴求しているのか確かめましょう。競合の状況から自社の優位性のほか、対策すべきポイントなどが見えてきます。
販促カレンダーの作成や施策の実施はAtoJを活用
販促カレンダーを作成するには、データをもとに現状分析し、その結果を来期に生かして施策を検討する必要があり、1から考えるのはなかなか大変です。ただでさえ忙しいECの運用担当者にとって大きな負担となることが考えられます。
来期に向けて分析や企画を自社で対応したいが、手がまわらないという場合はAtoJにお任せください。現状分析から企画、その後の制作まで一貫して対応することができます。
デザイナーやコーダーも在籍しているので、施策の実施に必要なランディングページやバナー、メルマガまで1社で完結することが可能です。連絡の窓口が1つになり、認識の共有もしやすいのでECサイトの運用を効率的に進めることができるでしょう。
施策実施後は効果検証と改善箇所などをまとめた振り返りも実施。PDCAをまわしながら運用し、ECサイトの成長を後押ししていきます。
まとめ
今回は販促カレンダーの作り方や作成時のポイント、作成するうえで参考になる月別のイベントなどをご紹介しました。販促カレンダーを作ることで計画的に施策を進行でき、円滑に運用を行うことができます。
ただ、販促カレンダーを作るためには現状分析をしたり、12か月分の施策を考えるなど、運用担当者にとって負担が大きい作業です。
忙しくて手が回らないという方は 「お問い合わせ」 からお気軽にご相談ください。ECの豊富な運用支援実績をもとに売上目標達成に向けたサポートをさせていただきます。
もっと知りたい!
続けてお読みください